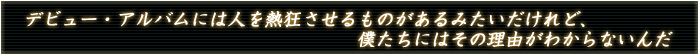 |
| |
| ――僕はサラスさんとほぼ同じ世代なんです。それまで、ジミ・ヘンドリックスとか、ジェフ・ベックとか、エリック・クラプトンとかが好きで聴いてました。まるで、年上の野球選手を見るように、その人たちを聴いていたんです。で、ある日気がつくと、同世代のすごいプレイヤーがフィールドで大活躍をしている!そう思ったのがサラスさんだったんですよ。サラスさんがデビューした'90年に、そういう衝撃を受けました。 |
 「どうもありがとう。昨夜、ディナーで会った人が、やはり'90年の日本ツアーの話をして、あのコンサートは自分の中でトップ3に入るコンサートだったと言ってくれたんだ。 「どうもありがとう。昨夜、ディナーで会った人が、やはり'90年の日本ツアーの話をして、あのコンサートは自分の中でトップ3に入るコンサートだったと言ってくれたんだ。
どういうわけか、例えばイギリスに行っても、今でも'90年のデビュー・アルバムとあのときのイギリス・ツアーについてみんなが話をする。あのアルバムから伝わったパワーのこととか。
俺自身は、そのインパクトがどんなものかよくわからないけど、影響を受けたと言ってくれる人がたくさんいる」 |
| ――どうしてご本人にはわからないんでしょう?(笑) |
「ただ単純にどうしてだかわからないんだ(笑)。このアルバムをプロデュースしてくれたビル・ラズウェルと、その後、何度かこのアルバムについて話したけれど、同じことが彼にも起こっていたんだ。彼はたくさんのアルバムをプロデュースしているにも関わらず、みんながこのアルバムについて話をするってね。どうしてだかわからないよ。それにこのアルバムはメチャクチャ売れたわけじゃない。
ただ、今でもに売れ続けている。だからこれからもずっと売れ続けるアルバムなんじゃないかと思うよ。人を熱狂させるものがあるみたいだけれど、僕たちには理由がわからないんだ」 |
| ――それはやっぱり、何か人に影響を与えるものが詰まっているアルバムだからだと思います。 |
| 「それが何かわかったら嬉しいんだけど。それがわかれば、ビン詰めにして売れるじゃない(笑)」 |
 |
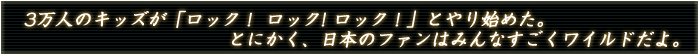 |
| |
| ――一昨日、大阪でギグをされていますが、その手応えというのはどんなものだったのでしょうか。ファンはすごく待ち望んでいたはずなので、かなり盛り上がったんじゃないかと思うんですが。 |
 「ああ、オーディエンスはクレイジーだったよ。俺の日本のオーディエンスは'90年の最初のライヴの時からクレイジーなんだ。当時、日本に来るバンドのライヴというと、曲が終わると、みんなワーっと拍手をする。で、その後シーンと静かになって、行儀よくバンドのほうを見つめ、次の曲が始まるとまたワーっとなるけど、また静かになる。その繰り返しだった。 「ああ、オーディエンスはクレイジーだったよ。俺の日本のオーディエンスは'90年の最初のライヴの時からクレイジーなんだ。当時、日本に来るバンドのライヴというと、曲が終わると、みんなワーっと拍手をする。で、その後シーンと静かになって、行儀よくバンドのほうを見つめ、次の曲が始まるとまたワーっとなるけど、また静かになる。その繰り返しだった。
ところが俺のオーディエンスときたら、最初からずっとクレイジーなんだ。そのクレイジーぶりに、プロモーターもレコード会社の人もみんな頭を掻きながら“どうなっているのかまるでわからない”というカンジだったよ。次の『バック・フロム・ザ・リヴィング』ツアーで4年ほどして戻ってきたときは、さらにクレイジーだった。ライヴの模様がたくさん収められている「テル・ユア・ストーリー・ウォーキン」のPVを見ると、観客が大騒ぎしているのがわかるよ。女の子は投げキッスをしてくるし(笑)、ビックリだよ。日本のキッズは普段はそんな反応をしないっていうけれど、何かが彼らを熱狂させたんだろうな。
その次の『オルタ・ネイティブ』ツアーで大阪のIMPホールでプレイしたときは、プロモーターから、観客の反応が異常だって言われたんだ。というのも、前列にいた女の子たちが何人も服を脱いでいたんだから。セクシャルな意味とか、俺におっぱいを見せようとか(笑)いうのではなく、神と対話をするかのように、踊りながらシャツを脱ぎ、そのシャツを頭の上で振り回していたんだ。恍惚状態かのようにね。僕のために脱いでくれたわけじゃない。ただ興奮してそういうことをしたんだ。そういう服を脱いじゃった女の子たちを目の当たりにして、俺たちは警察が来るんじゃないかと思ったくらいだよ。その後、ある大学のライヴではオーディエンスが騒いでいるうちに床が抜けて、俺たちはライヴを止めなけりゃならなかった。そんなふうに、俺の日本のファンはみんなすごいんだ。'99年のフジロックでは、俺が誰だか知らない人もたくさんいた。でも、靴が飛んだりしていたよ。You Tubeで見られるけど、俺がプレイを止めてオーディエンスのほうを見たら、3万人のキッズが「ロック! ロック! ロック!」とやり始めた。俺は後ろのバンドを見て、「見ろよ、すごいぜ!」みたいな(笑)。とにかく、日本のファンはみんなすごくワイルドだよ」 |
| ――一昨日の夜も同じようなことが? |
| 「ああ。正直に言って、ときどきステージ前方に進み出るのが怖くなることがあるんだ。俺のことを大好きで、傷つけようと思っていないのはわかっているけれど、手や腕をつかまれたりすると怖くなることがあるんだよ」 |
| ――今でも日本のオーディエンスって、曲の間はクレイジーになるんですが、曲が終わるとシーンとすることが多いんです。サラスさんの音楽には、人をクレイジーにさせる何かがあるんだと思いますよ。 |
| 「うん、そうだね。きっとエネルギーか何かなんだろうな。フジロックで2004年にプレイしたときは、有名雑誌の編集者から「サムライみたいにギターをプレイしている」って言われたよ(笑)。俺は「本当かい? そいつはいい」って(笑)」 |
| ――僕もそう思いますよ(笑)。 |
| 「ホントにそうかはわからないけれど、そう言われてとても嬉しかったよ。日本はプレイするのが楽しみな場所なんだ。なにしろ、ヨーロッパやアメリカでは何年にもわたってレコード契約絡みの問題がいろいろとあった。だけど日本ではいつもレコードが売れ、ライヴにはいいオーディエンスがたくさん来てくれる。いつも俺をサポートしてくれる日本のファンには本当に感謝しているよ。俺がどんな音楽をしようとしていようと、いつも俺を日本人のようにというか、自分たちと同じように扱ってくれるんだからね」 |
 |
 |
| |
| ――さて、新作の『ビー・ワット・イット・イズ』が昨年出ました。まさにスティーヴィー・サラスというか、スティーヴィー・サラス・イズ・バックというか、ヘヴィーで、ファンキーで、クールで、ロック・ファンの心と身体の両方を踊らせる内容だと思います。その中に「マイ・ガール・イズ・ゴーン」とか「トゥ・ビギン・アゲイン」といった、すごくメロディーの美しい曲も入っていて。サラスさんの持っている多彩な魅力が詰まりきったアルバムのような気がしています。 |
| 「ジミ・ヘンドリックスとジェイムズ・ブラウンから生まれた子供がいるとしたら、それが俺のアルバムだよ。ジェイムズ・ブラウンのエネルギーとかパワーが昔から大好きなんだ。そして、ジミ・ヘンドリックスはとてもアグレッシヴなギタリストだけれど、「リトル・ウィング」や「砂のお城」といった美しい曲を歌うととても感動的で、俺はそういうタイプの曲もすごく好きなんだ。このアルバムを作っていたころ、俺は古いカタログにあった曲をたくさんリマスタリングしていたんだ。できて16、7年になる曲だよ。で、最初の3枚のアルバムに入っているような昔の曲を聴いていて、ドラマーとベーシストと一緒にスタジオでレコーディングしていた、昔のバンドのような形に戻りたいと思ったんだ。オーヴァーダブがほとんどなくて、バンドっぽい雰囲気を伝えるようなものをね。というのも、最近のミュージシャンの多くは音楽をどうプレイすればいいのか、よくわかっていない。コンピュータばっかり使ってね。そういうのが俺を不安にさせるんだ。でも、俺は腕の立つミュージシャンにスタジオに入ってもらうことができたし、レコーディングではバンドのフィーリングを出したいと思った。それが俺のコンセプトなんだ。今回の作品では、それが出せたと思う。俺のコンセプトの基になるのは、自分が聴いていた70年代のプレイで、そのフィーリングの出し方を見つけ出したら、そこに今ふうのエネルギーとパワーを加えるんだ」 |
| ――曲はすでにあったものなんですか? それともスタジオに入ってから作ったんでしょうか? |
 「いろいろだね。例えば「ウォーン・アウト・ルースター」は、レコーディングの終わりのほうにカナダのスタジオでまるまる作った。俺はその時ミキシング作業をしていたんだけど、急に思いついて隣のスタジオに行き、その場で自分の物ですらないギターをつかんでアンプにつないで、この曲をレコーディングしたんだ。スライド・バーもなかったから、マイク・スタンドから金属の一部を取って指につけてウィーン、ウィーって弾いたんだ。そして聴き直して「よし!」と思ったんで、今度は紙を取って歌詞を書いた。で、それを歌ったんだ。面白おかしくといった感じでね。その後、「さて、次は何をしようか」ということになり、今度はマイクを床に置いた。この曲は2時間で録ったんだけど、マイクを床に置いたら、足踏みのようなことをして大きな音を立てた。それを10トラック分ぐらいやったよ。聴いてくれればわかると思う。「はっはっ/ドスドス」っていうあれは、俺の足音なんだ。そしてまた「ふ〜む」と考えた。もうギター・ソロには飽き飽きとしていたんで、それはイヤだった。で、動物の鳴き声のサウンド・エフェクトを使うことにした。エンジニアからは「何やっているんだ?」と訊かれたよ。なにしろ動物の、“ウ〜”とか“キキキ”とか、鳥の“ピーピー”いう鳴き声とかを加えたんだから。というのも、ビートルズの本を読んでいたら、「Good Morning〜♪」に続けて“コッコッコッコ〜”とニワトリが鳴く曲の話が出てきて、それで「ニワトリを自分の曲にも入れたい!」と思ってたんだ(笑)。それを聴きながらひとりで爆笑していたよ。カナダの連中は、俺がおかしくなったと思っただろうな。涙を流して笑いながら、ウシやらブタやらニワトリの鳴き声を入れてるんだから! 「いろいろだね。例えば「ウォーン・アウト・ルースター」は、レコーディングの終わりのほうにカナダのスタジオでまるまる作った。俺はその時ミキシング作業をしていたんだけど、急に思いついて隣のスタジオに行き、その場で自分の物ですらないギターをつかんでアンプにつないで、この曲をレコーディングしたんだ。スライド・バーもなかったから、マイク・スタンドから金属の一部を取って指につけてウィーン、ウィーって弾いたんだ。そして聴き直して「よし!」と思ったんで、今度は紙を取って歌詞を書いた。で、それを歌ったんだ。面白おかしくといった感じでね。その後、「さて、次は何をしようか」ということになり、今度はマイクを床に置いた。この曲は2時間で録ったんだけど、マイクを床に置いたら、足踏みのようなことをして大きな音を立てた。それを10トラック分ぐらいやったよ。聴いてくれればわかると思う。「はっはっ/ドスドス」っていうあれは、俺の足音なんだ。そしてまた「ふ〜む」と考えた。もうギター・ソロには飽き飽きとしていたんで、それはイヤだった。で、動物の鳴き声のサウンド・エフェクトを使うことにした。エンジニアからは「何やっているんだ?」と訊かれたよ。なにしろ動物の、“ウ〜”とか“キキキ”とか、鳥の“ピーピー”いう鳴き声とかを加えたんだから。というのも、ビートルズの本を読んでいたら、「Good Morning〜♪」に続けて“コッコッコッコ〜”とニワトリが鳴く曲の話が出てきて、それで「ニワトリを自分の曲にも入れたい!」と思ってたんだ(笑)。それを聴きながらひとりで爆笑していたよ。カナダの連中は、俺がおかしくなったと思っただろうな。涙を流して笑いながら、ウシやらブタやらニワトリの鳴き声を入れてるんだから!
まあそんなふうに、曲によってはまったく計画なしのこともある。もちろん、大事な曲はスタジオ入りする前に作っておくけどね。「ビー・ワット・イット・イズ」は先に作った。これは大事な曲になるってわかっていたからね。「ゲット・アウト・アライヴ」もそうだ。それから稲葉浩志と一緒に作った「ヘッド・オン・コリジョン」もそうだ。この曲はもともと稲葉浩志のソロ・アルバムで日本語ヴァージョンが録音されているけれど、俺たちは一緒に新しい英語ヴァージョンを歌うことにしたんだ。そんな具合に、事前に準備されたものも、されていなかったものがあるんだよ」 |
| ――稲葉浩志さんの話が出ましたが、稲葉さんの参加というのは、サラスさんのほうから要請されたんですか? |
| 「そうだよ。俺たちはもう何年も友達で、一緒に食事に行ったり、ロサンジェルスや日本でよく遊ぶ仲なんだ。で、今回はというと、まず、彼のほうから彼の前回のソロ・アルバム用に曲作りを頼まれたんだ。それで2曲一緒に書いて、ビデオも一緒に作った。すると彼から「正面衝突」という曲がそのアルバムに入っていると聞いたんだ。それで「それはどういう意味だい?」と訊くと、“Head On Collision”だと教えてくれた(笑)。それで、彼から「この曲の英語版をやらないか」と言われたんだ。「じゃあ、俺と一緒に歌おう」って言って。彼のマネージメント・サイドからもOKが出た。それで、俺はまったく新しい歌詞を作ったんだ。「ヘッド・オン・コリジョン」というタイトル以外、日本語の歌詞については何も手がかりなしにね。タイトルはそのまま「ヘッド・オン・コリジョン」にして、メロディーも新しく作り、俺が歌ったものを浩志に送った。で、彼はそれをスタジオに持って行き、英語で歌って録音した。彼にとって英語で歌うっていうのは、エキサイティングだったはずだよ(笑)。それでデュエットのような作品が出来上がったんだ」 |
 |
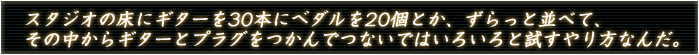 |
| |
| ――アルバムで使用した機材についてうかがいます。ギターはワッシュバーンのシグネチャー・モデルでしょうか。 |
 「いや、違う。ワッシュバーンはもう使っていないんだ。もう何年も使っていないな。俺は実験的だから、毎年まったく新しいギターを試しているんだ。いつも新しいサウンドを求めているからね。 「いや、違う。ワッシュバーンはもう使っていないんだ。もう何年も使っていないな。俺は実験的だから、毎年まったく新しいギターを試しているんだ。いつも新しいサウンドを求めているからね。
最近、日本製の素晴らしいギターに出会ったよ。キャパリソンというんだけど、すっごく気に入っているんだ。あと、今夜はゴディンというカナダのメーカーのギターを使う予定だし、ディーンのギターも使うかもしれないな。なにしろ、毎月、あちこちの会社から新しいギターが自宅に届くんだ(笑)。だからいろいろと試しているんだよ」 |
| ――では、今回のアルバムの中でメインに使ったギターというと……? |
「うーん、ギターは100本ぐらい持っているからなぁ(笑)。
アルバムの『シェイプ・シフター』('01年)のころから、スタジオの床にギターを30本にベダルを20個とか、ずらっと並べて、その中からギターとプラグをつかんでつないではいろいろと試すやり方なんだ。「うん、これでいい」とか、「こいつはダメだな」とか、試しながら決めるんだ。その都度サウンドを見つけるんだよ。俺は、ただレコーディングだけして、あとのEQとか直しはエンジニアに任せればいいとは思っていない。その場でピッタリのサウンドを見つけたいんだ。後で直すなんてまっぴらだね。最初からいいサウンドでいきたいんだ」 |
| ――アンプは何を? |
| 「いつもフェンダーの'65年製デラックス・リヴァーブだね。今作を含めて、これまでのすべてのアルバムで使っている。あと、やはり古いマーシャル。それからイギリスのコーンフォードのアンプに、同じくイギリスのアッシュダウンのアンプも使う。でも、基本的にはそこにある物を使っているよ」 |
| ――アンプも一緒なんですね(笑)。 |
| 「うん、気にしないね。サウンドの個性っていうのは、この手で作られるものだと思っているからね。だから常にこのギターでなければならないとか、常にこのアンプでなければならないということは気にしていないんだ」 |
| ――そう言われた後では訊きにくいんですが(笑)、エフェクト・ペダルについてはいかがでしょうか。 |
| 「山ほど持っているよ。エフェクターって興奮する物だよね。毎回何か試すたびに、違う窓を開けて新しい景色を見るような気分になる。実は、ペダルを変わった方法で使うことがよくあるんだ。逆につなぐような使い方とか。例えば、「キックバック」(『ザ・サムタイムス・オルモスト・ネバー・ワズ』収録)では、“ガ、ガッガ、ガーガー”みたいな音が入っている。あれはペダルのプラグを逆につないで出した音なんだ。面白いサウンドだ。でも、ライヴでそうやって作った音を再現するのは難しいよ。どのペダルを使ったか、ちゃんと覚えていないからね」 |
| ――逆につなぐっていうのは? |
| 「ああ、ペダルのインとアウトを逆につなぐんだ。うまく音が出ることもあれば、出ないこともある。でも、出るときはすごい音が出るんだ(笑)。とにかく何でもやるよ。ワウワウ・ペダルを前に1台、そして後ろにももう1台置き、ひとつにディストーション・ペダルを3つか4つつなぐとすごい圧力がかかるから、大きなバケツの中に入っている水が細い管を通っていくような状態になるんだ。スタジオでそれを大音声で響かせると、断末魔のようなサウンドになるんだ(笑)。それを音楽的に使えれば、だけどね」 |
| ――じゃあ今回も、特にこういうペダルを使ったというのは、自分でもわからないですか?(笑) |
 「忘れちゃったよ。ペダルは何100も持っているからね。でも、ワウワウ・ペダルはいつも使っている。あと、ジム・ダンロップのカスタム品をたくさん持っているよ。フルトーンのも使うし、MXRのいろんな歪み系も使う。でも、ジム・ダンロップが俺のペダルのほとんどを作ってくれている。もう、まるで科学者みたいだよ。「もっとミッド・レンジのあるペダルがほしい」と言うと、「これを試せ」と言われる。で、ダメとなると、また手直ししてくれる。いいものになるまでね。俺はゲインとミッド・レンジをいろいろと試してみているんだ。 「忘れちゃったよ。ペダルは何100も持っているからね。でも、ワウワウ・ペダルはいつも使っている。あと、ジム・ダンロップのカスタム品をたくさん持っているよ。フルトーンのも使うし、MXRのいろんな歪み系も使う。でも、ジム・ダンロップが俺のペダルのほとんどを作ってくれている。もう、まるで科学者みたいだよ。「もっとミッド・レンジのあるペダルがほしい」と言うと、「これを試せ」と言われる。で、ダメとなると、また手直ししてくれる。いいものになるまでね。俺はゲインとミッド・レンジをいろいろと試してみているんだ。
でも、何と言っても、バンドっていうのはベースのサウンドがよくなければいいサウンドにはならない。ベースのサウンドはギターにピッタリと合ったものでなければならないのに、みんなギターにばかり注目して、そのことって忘れられがちなんだ。ベースがよければ、ギターのいいサウンドの基礎ができているのと同じだ。だからギターのサウンドをうんとよくするためにも、いつもいいベーシストを使わなければならないんだ」 |
| ――サラスさんが使って有名になった、グヤトーンのワウロッカーは? |
| 「ああ、ワウロッカーはいつも使っているよ。俺の秘密兵器さ。「テル・ユア・ストーリー・ウォーキン」のイントロの部分もワウロッカーだし、レニー・クラヴィッツだって「フライ・アウェイ」でワウロッカーを使ってる。俺がプレゼントしたヤツを使っているんだ。彼はキーボードやギターなどにも使ってるね」 |
| ――話が変わりますが、サラスさんはデビュー時に「ジミ・ヘンドリックスが生きていたら、たぶん今こういう音楽をやっていただろう」と言われていましたが……。 |
| 「本当かい? 知らなかったよ。ジミ・ヘンドリックスの真似をしているとは思われていなかったはずだけど、ジミ・ヘンドリックスとか昔のアーティストのスピリットを持っているというふうに捉えられていたのは知っているよ。そういう言われ方をして、とても光栄だったな。そういう意見にはあまり耳を傾けないようにはしたけれど。でも、ニューヨークに行って、2枚目のカラーコードのアルバムを制作していたとき……、いや、結局2作目のカラーコードではなく、バディ・マイルスとブーツィー・コリンズが入っているんで最終的には『ハードウェア』になったんだけど、このときバディが自分の持っているジミ・ヘンドリクスのギターを僕にプレイさせようとして持って来てくれたことがあったんだ。「ジミからもらったものだけれど、弾きたいかい」ってね。でも、俺は触ることさえできなかった。触るのさえはばかられたんだから、プレイなんてできないよね。だって、そんなギターでプレイしたら、それこそジミみたいにプレイしようとしちゃうじゃないか(笑)。彼のパワーや誠実さは自分のものにしたいけれど、彼のようには……。とにかく、とても光栄だったけれどね。あと、ジミ・ヘンドリクスを発見したばかりといった、音楽を聴き始めて間もないようなキッズたち、そんな日本のキッズたちにも俺を見つけてほしい。これまで俺のことを知らなかったキッズが『ビー・ワット・イット・イズ』を聴いて、興奮してくれたら嬉しいよ」 |
| ――で、ジミ・ヘンドリックスが生きていたらこんな音楽をやっていただろうと言われることについて、どういう感想を持ちますか? 嬉しいでしょうか、それともそんなことを言われると困るのでしょうか(笑)。 |
| 「もちろん、そう言われたらとても嬉しいよ。なにしろ彼は最高に素晴らしいギタリストだからね。だけどそういう言葉は真に受けられない。そう思ったら、鼻持ちならないヤツになるじゃないか。ジミ・ヘンドリックスはジミ・ヘンドリックスだし、彼は最高だよ。とても嬉しいけど、そういう言葉にはマジに受け取らないようにしているんだ」 |
| ――少しでもサラスさんに近づきたいと思っているギタリストたちに、アドヴァイスとメッセージをお願いします。 |
| 「俺がギターを始めたばかりのころ、まず最初にしたことは練習だった。とにかくずっと練習していた。仕事のようにいやいやするのではなく、なにしろプレイするのが好きだったから、毎日3時間とか練習したよ。それを3年ほど続けた後は、それほど練習しなくなった。その代わりに、頭の中でプレイを考えるようになった。耳で聴いたものを捉え、イメージ化するようにしたんだ。そしてそれをそのまま弾くようにした。あまり考え込まずにね。考え過ぎると、曲のもつエネルギーとかスピリッツを捉えられなくなる。だから、このサイトの読者に言うとしたらだな……。映画の『スター・ウォーズ』で、目隠しのヘルメットをかぶせられたルーク・スカイウォーカーがフォースを頼りに、頭で考えずに闘うじゃないか。俺もそうなりたいんだ。フォースを使って、エネルギーを感知し、深く考えずにエネルギーを俺の身体を通して発揮させたい。だからアドヴァイスは、「考え過ぎずに、身体を通して音楽を伝えろ」ってことかな」 |
 |