 |
 |
|
| |
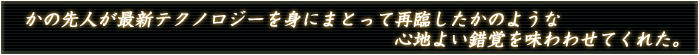 |
 単独では'99年以来となる、スティーヴィー・サラスの来日公演。ファン待望の、と言ってもいいだろう。 単独では'99年以来となる、スティーヴィー・サラスの来日公演。ファン待望の、と言ってもいいだろう。
思えば'90年にデビューしてからすでに17年の年月が流れた。世界中のロック・ファン、ギタリストがあのとき受けた衝撃。その大きさは計り知れない。「ジミ・ヘンドリックスの再来」という言われ方をしたが、確かにそのファンキーでヘヴィーなグルーヴは、かの先人が最新テクノロジーを身にまとって再臨したかのような心地よい錯覚を、幾分かぼくたちに味わわせてくれた。
だが、正直なところ、それが「言い過ぎ」であることはみんな分かっていた。だって、相手はジミ・ヘンドリックスだ。誰も彼と比較してはいけない。存在があまりにも大きすぎるから、比較された相手が逆に惨めにさえなる。けれどもサラスの場合は、「言い過ぎ」なのは分かっていても、その表現がどこかしっくりと来る気もした。それは、“ジミヘン・フォロワー”と呼ばれる、ジミに似すぎているギタリストたちよりも、よっぽどジミの精神の部分を受け継いでいるような気がしたからかもしれない。
そんなことを考えながら、ぼくは彼のステージを見つめていた。
オープニング・ナンバーは最新作のタイトル曲「ビー・ホワット・イット・イズ」。のっけからヘヴィー&ファンキーなサラスの世界へ引きずり込まれる。それは彼を待ち焦がれたファンたちへの、強烈な再会の挨拶でもあった。
続けて「テル・ユア・ストーリー・ウォーキン」、「ハーダー・ゼイ・カム」と、代表曲の2連発。サラスからの挨拶に、観客は最大限クレージーになることで応える。
使用ギターは最近のお気に入りだという緑のキャパリソン。そこから飛び出してくる図太いサウンドとシャープなカッティングは、万華鏡を覗いているかのような変幻自在ぶりだ。
次の「ボディ・スラム」、「フリーズ・ドライド」ではゴディンとディーンを使用。そして、再びギターをキャパリソンに戻したと思うと、「ボーン・トゥ・マック」、そして「インディアン・チーフ」。'90年代のあの衝撃を、ライヴの場で見事に再現してくれる。彼は自分のギター・プレイをひと言で表現すると、「ワイルド」だと言う。まさにそのとおり。ステージを観ていればそれが実感できる。しかしそのワイルドさの奥に繊細な表現力が隠されていることも、きっとファンは見抜いている。
「トゥー・ソウルズ・ウォーン・イン・ア・バッグ・オブ・スキン」はニュー・アルバムから。この曲では、バンド・オブ・ジプシーズのライヴを観ているような錯覚に陥ってしまった。ユニ・ヴァイブ、ワウ、そしてワウ・ロッカーを組み合わせてのインプロヴィゼーションは、ブルージーでサイケデリックだ。
「キックバック」、「サング」のあと、「スタート・アゲイン」でサラスはギターを観客の中に放り入れる。初めて見る光景だ。ギターのダイブに、ギターのモッシュ。緑のキャパリソンは客の頭上を、まるで嵐の中の船のように漂う。そんな航海のあと、手元に戻ってきたギターを、何事もなかったように弾き始めるサラス。ギターも彼もタフ。そしてワイルド過ぎるほどにワイルドだ。ここで本編は終了した。
 アンコール1曲目は、よりファンキーにアレンジされ、ジャムっぽく演奏された「スタンド・アップ!」。かつてサラスを世に知らしめたこの1曲が、観客を躍らせ、叫ばせる。そして、タイトに「ジャスト・ライク・ザット」を決めたあとは、「ブレイク・イット・アウト」、「アー・ザ・ゴッズ・スマイリング・オン・ミー(オア・アー・ゼイ・ラーフィング)」。 アンコール1曲目は、よりファンキーにアレンジされ、ジャムっぽく演奏された「スタンド・アップ!」。かつてサラスを世に知らしめたこの1曲が、観客を躍らせ、叫ばせる。そして、タイトに「ジャスト・ライク・ザット」を決めたあとは、「ブレイク・イット・アウト」、「アー・ザ・ゴッズ・スマイリング・オン・ミー(オア・アー・ゼイ・ラーフィング)」。
「この曲は生涯2回しか演奏したことがない。その1回はこの前の大阪だ。イギリスでデビュー前に書いた曲で、この曲のおかげでレコード契約が取れたんだ」。そんな、珍しくしっとりとしたMCのあと、大ラスの「コート・イン・ザ・ミドル・オブ・イット」へ。彼の中ではポップな曲調のナンバーだ。演奏前のMCもあり、サラスがこの曲を大事に思っていること、そしてその曲を今日最後に演奏したかった気持ちが、ひしひしと伝わってくる。
「ありがとう! 日本は俺のセカンド・ホームだ!」
そう叫んだ彼の言葉には、いっさいのお世辞も嘘も含まれていなかったと、ぼくは思う。
振り返ってみると、ギターのチューニングが怪しい場面はいくつもあった。
声が出ていない部分もあったし、音程が危ないところもあった。
ライヴだからそれでいいんだ、とは言わない。そういうところはやはり、プロとしては再点検して、改善していかなければいけない部分だと思う。
でも、とぼくは思う。
誰がサラスの代わりをできるんだ?と。
彼の打順に送る代打はいないじゃないか、と。
そう、だからこそ、彼にホームランを打ってもらいたいという気持ちも、必要以上に強くなってしまうのかもしれない。
デビューして17年。彼の音楽性はいっさい変わっていない。それだけを取ってみても、「ジミ・ヘンドリックスの再来」とは言えないだろう。たった4年でロックのあり方をくつがえしてしまったジミが、17年間も同じことをやり続けるなんて、考えられないからだ。
けれども、ステージ上のサラスはやはり、ジミの精神の一部をきっちりと受け継いでいると思えた。
繊細さに裏打ちされたワイルドさ。
それもそのひとつの表れかもしれない。 |
 |
|
| |
|
|
本サイトで使用されている、写真、画像、文章等を無断転用することを禁じます。
Copyright 2007 © TARGIE All rights reserved. |
| |
|
 |